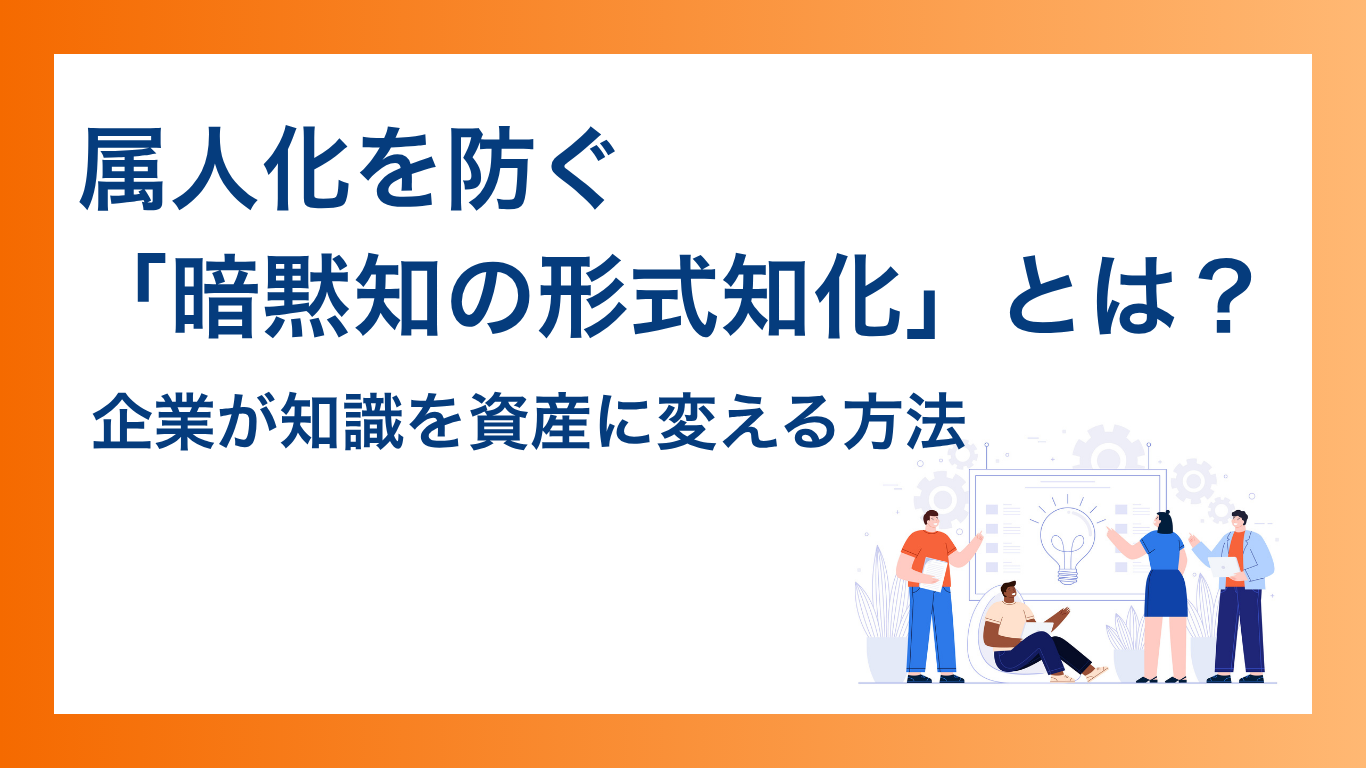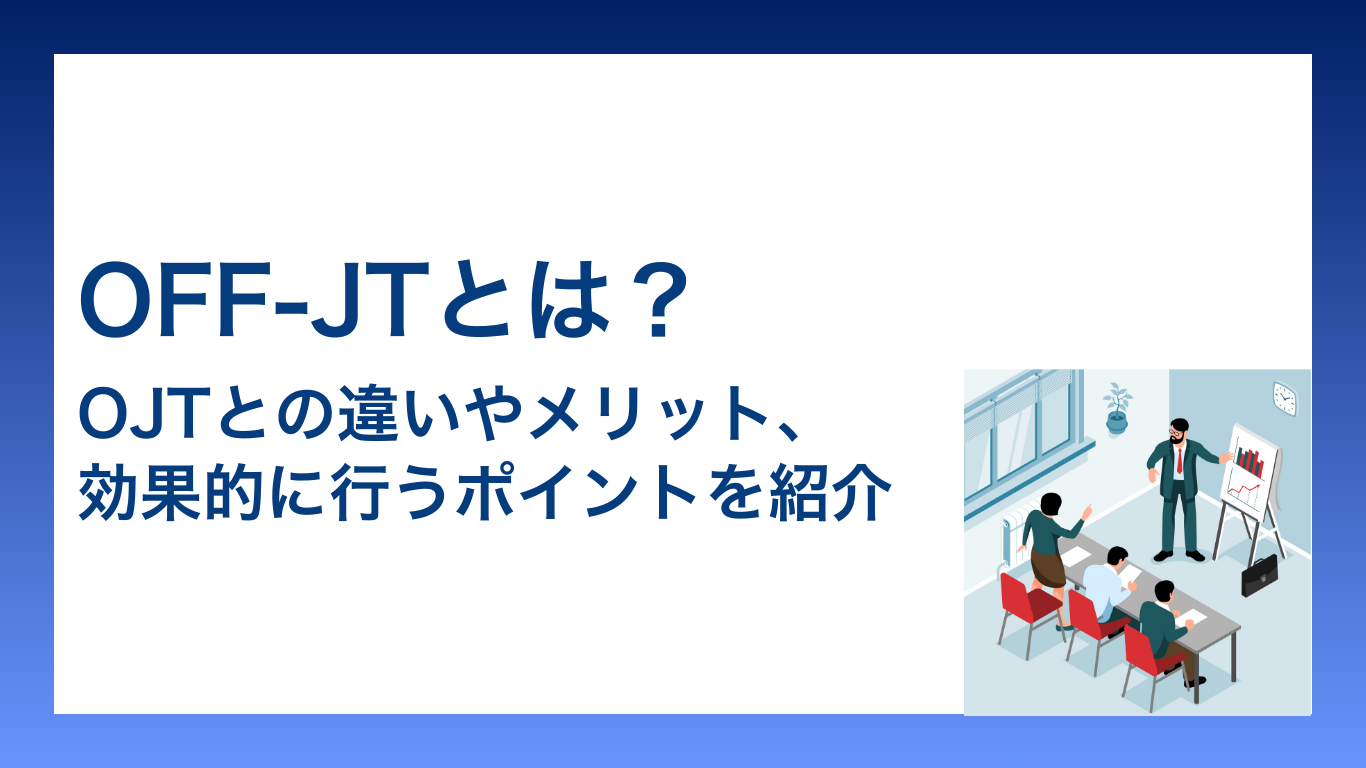企業の人材育成や研修の分野で注目されている「アダプティブラーニング」。一人ひとりの学習状況に合わせて最適な教材や進度を提供することで、従来の一斉研修では難しかった“個別最適化”を実現できる学習手法です。
本記事では、アダプティブラーニングの基本的な意味から従来の教育との違い、導入メリットや具体的な活用事例までをわかりやすく解説します。
アダプティブラーニングとは
アダプティブラーニング(Adaptive Learning)とは、学習者一人ひとりの理解度や進捗に合わせて教材や学習体験を最適化する教育手法です。この概念自体はまったく新しいものではありません。では、なぜ近年再注目されているかというと、技術の進歩により、人の手を介することなく、少ないリソースでもこの学習手法が実現できるようになったためです。
従来型のすべての人に対して一斉に同じ内容の学習を行うやり方とは異なり、データ、アルゴリズム、テクノロジーを活用し、各人のこれまでのスキルや知識レベル、学習履歴や習熟度に応じて学習パスを柔軟に調整できる点が特徴です。
たとえば英語学習を例にとると、これまでの学習履歴やペース、テストの正答率を分析し、学習者の現在のレベルより少し上のレベルの課題やカリキュラムを提案したり、つまずきポイントに重点を置いた問題を出題したりする調整は、従来学習者に対して講師1人1人が行っていました。
こういったアダプティブラーニングのきめ細やかなフォローアップが、AIやIT技術を用いることで、1度に数十人、数百人、あるいは数千人の学習者に同時に提供することが可能になりました。
従来型の学習との違い| メリット・デメリットは?
eラーニングの普及やAI技術の進歩により、企業での実用も可能になりつつあるアダプティブラーニングですが、従来型の学習と比較して、どういったメリット・デメリットがあるか理解した上で実践するのがおすすめです。
アダプティブラーニングのメリット
パーソナライズされた学習の実現
社員ごとに異なる知識レベルやスキルセット、現在の習熟度を考慮して学習内容を提案してくれるため、1人1人に合わせた「オーダーメイド教育」が可能です。学習者にとっては自分のレベルに合わせた学習が可能になるので、理解できずに業務に必要な知識が身につかない、もしくは簡単すぎて時間が無駄になる、といったことがなくなります。
学習効果の最大化
上記のように、各人に最適化された学習が可能になるため、学習者はまるで専任の講師がついているかのように学習することができ、自主的な学習を促すことも可能になります。よって、これまでよりも学習内容の理解や定着が進み、学習者の集中力やモチベーションの維持が期待できます。
研修にかかるリソース・コストの削減
これまでの社員教育はリソースの問題もあり、実施後のフォローや定着のためのサポートが十分なされていませんでした。こういった課題を、人的リソースをかけることなくテクノロジーを活用することによって解決でき、研修効果を高めることが可能になります。
データの蓄積・可視化ができる
誰が、いつ、どんな研修を、どれくらい受講し、スキルを習得したか?データが蓄積・可視化されます。こういったデータ群は企業にとって戦略上、非常に重要な情報となり、例えばこれまで難しかった研修自体の費用対効果を測ったり、企業の人材戦略と照らし合わせ、どういったスキルや人材が不足しているかの分析が可能になります。(これが実は一番のメリットかもしれません!)
アダプティブラーニングのデメリット
システムの導入や環境の整備が必要
高度なデータ解析や機能を持つアダプティブラーニング用のプラットフォームを導入するには、一定のコストやITリソースが必要になります。また、社内導入のためのガイドライン整備や運用時のサポート体制の構築など、人的リソースが必要になることも理解しておきましょう。
対面型研修の代替にはならない
ロールプレイングやシミュレーション形式で行う必要のある、オンライン上で完結できない研修の代替にはなりません。たとえば、製造現場での危険作業研修や災害発生時訓練、小売やサービス業での接客研修、救急救命訓練など。アダプティブラーニングの仕組みは、対面型研修で学んだことを補うために活用する、という形がおすすめです。
アダプティブラーニングはどういう仕組みでできている?
アダプティブラーニング向けの学習システムはさまざまですが、おおよそ以下のような流れで学習者をサポートしてくれます。
データ収集
アダプティブラーニングをフル活用するために重要になるのが、各人の学習ログです。学習者がいつ、どんな教材を、どれくらいの時間受講しているか、また各学習の理解度チェックのテストの点数など、さまざまなデータを継続的に収集します。たとえば以下のようなデータが収集されます。
・学習教材の種類
・学習にかかった時間やどれくらいの期間をかけて修了したか
・理解度テストの結果に基づく得意・不得意分野
・現在のスキルや知識レベル
リアルタイム分析
上記のデータに基づき、学習者の現在の知識、スキルレベルと目指すべきキャリアとのギャップ分析を行います。
パーソナライズ化
分析されたギャップに基づき、システムが今学習者に必要な学習内容や学習すべき優先度や順番、学習ペース、受講テストの難易度を調整します。この調整は以降の学習進捗に応じて動的に変更・最適化が行われます。
フィードバック
分析されたギャップに基づき、学習システムが今学習者に必要な学習内容や学習すべき優先度や順番、学習ペース、受講テストの難易度を調整・提案してくれます。
継続的な改善
学習システムは個別カリキュラムを生成した後も、学習者の進捗や成績をチェックし、その習熟度に応じてフォローアップが必要な分野については追加の受講教材を提案したり、より高度な学習を提案したりとカスタマイズを続けます。
企業で導入する際の注意点は?
多くの利点があるアダプティブラーニングですが、自社で導入するにあたってはいくつか注意したいポイントも。ここでは4つの注意点を解説します。
導入目的を明確にする
「新人教育の効率化」「資格取得支援」「スキルギャップ解消」など、導入の目的を明確にしましょう。目的に応じて必要となる教育教材やツールが決まってきます。また、実施後の効果計測を行う際にも、期待した効果が得られたか?を検証しやすくなります。
学習教材を充実させる
学習者のレベルに応じた学習教材を提案するために、習得する知識やスキルのために必要となる学習教材を充実させることは必須です。数と種類が不十分だと、学習者に提案される教材やカリキュラムも非常に限られたものになってしまいます。
継続的に学び続ける動機づけをする
自動で個別最適化される便利な学習手法ですが、学習者に継続して学んでもらうための動機づけや、学び続けること自体が企業のカルチャーになるような取り組みが重要です。継続的な学習を促進するための手法として、たとえば以下のようなものが挙げられます。
・学習内容がすぐに業務の中で使えるような運用を組む。
・学習内容を「昇進・評価・キャリア形成」とリンクさせることで、目的意識を高める。
・1 on 1を通じた上司からのフォローアップや、上司自身が学び続ける姿勢を示す。
・5~10分ほどのすきま時間で学習できるマイクロラーニングコンテンツを準備する。
・ポイント・バッジ・ランキングなどを活用し、学習を「競争」や「ゲーム感覚」で行える、ゲーミフィケーションの要素を取り入れる。
実施後の評価と改善
運用開始後の振り返りを実施して、研修自体の従業員の満足度調査や目的に対する達成度合いを測り、評価に応じた改善活動を行うようにしましょう。また、従業員の学習ログやアップデートされたスキルデータが蓄積されると、貴重なデータベースが出来上がるので、別の活用方法、たとえば企業の人事戦略とのギャップ分析も可能になります。
アダプティブラーニングを実現する便利なツール5選
ここでは、企業がアダプティブラーニングを実践するための機能を持つ学習システムをいくつかご紹介します。
Realizeit
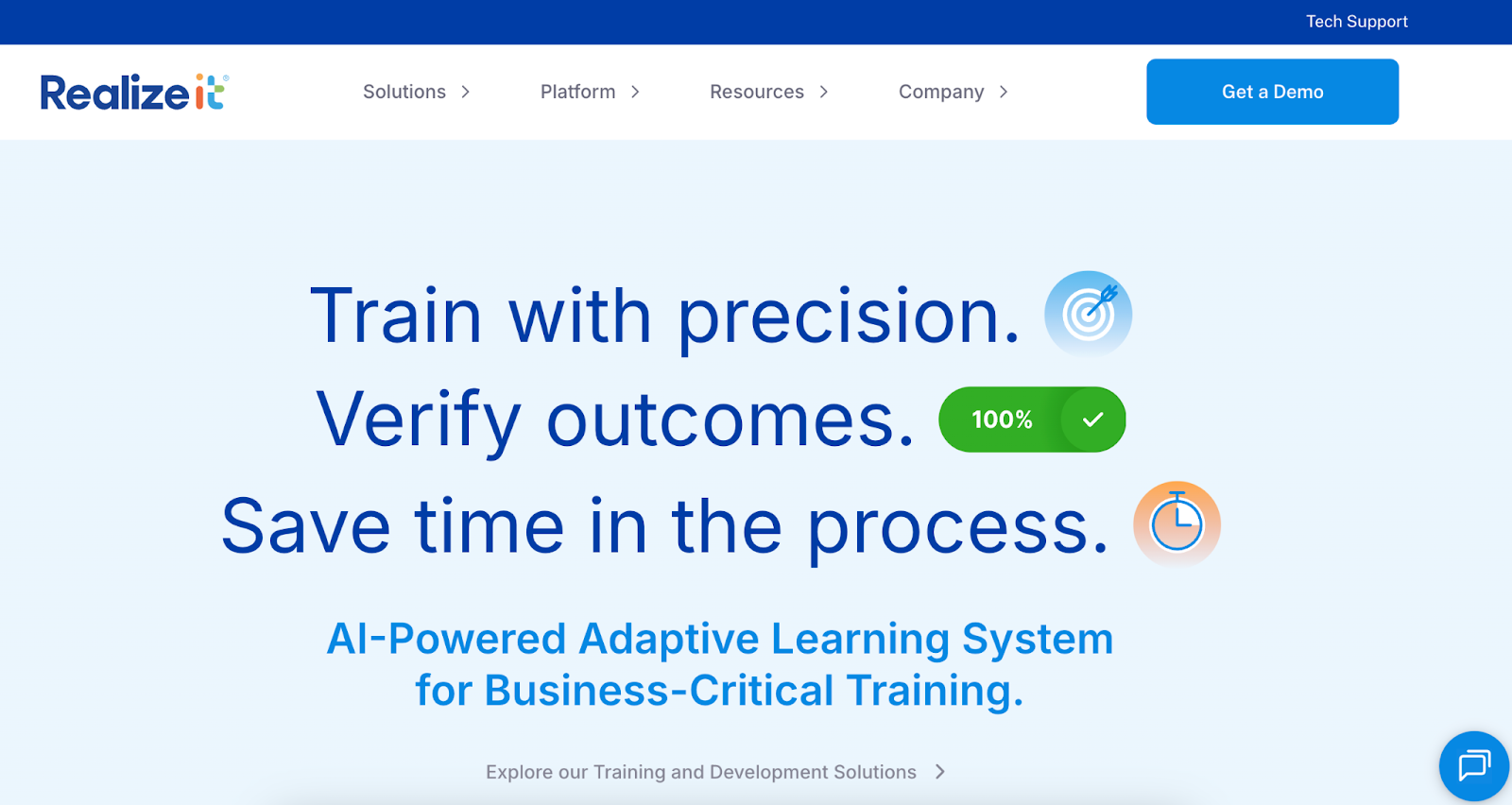
https://www.realizeitlearning.com/
Realizeit は、品質・安全管理や現場作業訓練など、業務上必須で受講する必要のある研修・学習向けに開発された適応型学習プラットフォームです。このシステムの特徴は、学習者がすでに知っている知識を自動的に判定し、関連する研修をスキップする機能や、一度学んだ知識を一定期間経過後に再学習・復習を行う仕組みを備える点などがあります。
また、個人と集団のパフォーマンス比較や学習ギャップ検出、学習傾向分析などをリアルタイム可視化できる分析機能も充実しています。
Smart Sparrow
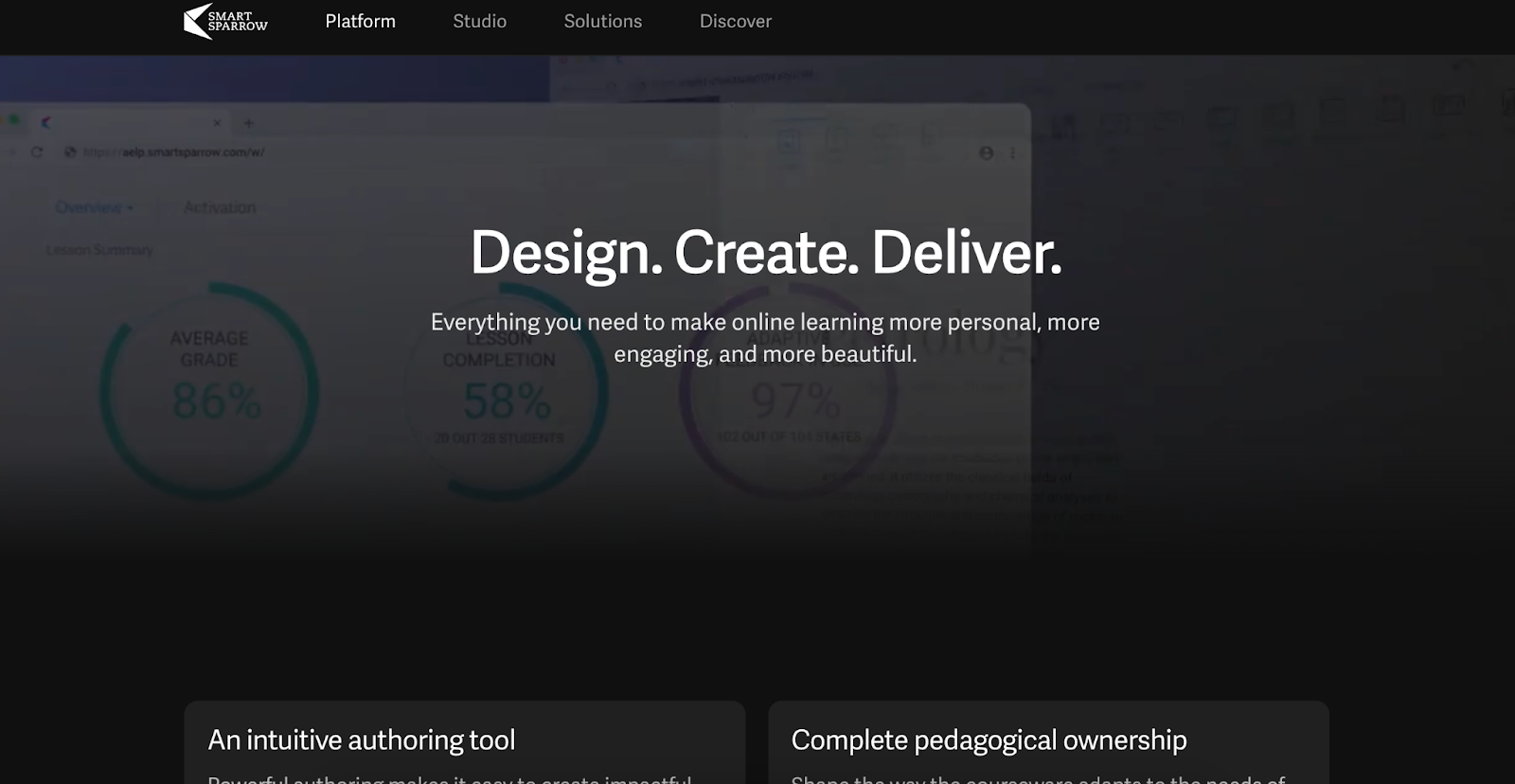
Smart Sparrow はオーストラリア発の学習システムです。このシステムは、学習者のテスト回答や受講ログに応じて学習パスを分岐させたり、理解度が低い内容については補助教材表示ロジックを組むことができたりと、教材設計者側の柔軟性が高いのが特徴です。また、受講内容にシミュレーションや選択項目を組み込んだりと、インタラクティブ性が高いのも特徴です。
SC Training

https://training.safetyculture.com/ja/
サービス業などお客様と直接やりとりが発生するような業務につく人や、製造・建設現場向けのトレーニング最適化を強く意識した作りになっており、“短時間で学べて定着しやすい教材形式” を追求する設計が特徴です。
そのためモバイルファースト、 1回あたりの研修を短い時間で行えるマイクロラーニング形式がメインです。受講者の記憶定着を促すために、復習タイミングを制御する仕組みを含む教材設計も可能です。
CoreLearn

https://solution.toppan.co.jp/education/service/corelearn.html
知識の完全理解・定着を打ち出す国産の学習システムです。間違えた問題に応じて復習課題を出す機能で、必要な知識が確実に定着するまでシステムがフォローします。そのため金融知識が必須の銀行などで導入・活用されています。
BlendVision AiM

https://blendvision.com/ja-jp/aim/
動画の取り扱いが得意な学習システムです。AIチャットボットに問いかけるだけで、膨大にある教材から目的の研修コンテンツを提案してくれたり、動画内検索で該当箇所をすぐに呼び出したり、AIが自動で研修教材にタグ付けしてくれるので、定着のための振り返りが簡単に可能です。また、学習内容定着のための小テストをAIがカリキュラムに合わせて自動で生成してくれます。
まとめ
アダプティブラーニングは、研修を運営する人のリソースを削減しながらも、社員一人ひとりに合わせた学習が実現できる理想的な手法・システムです。適切な設計と運用を行えば、人材育成の質を大幅に向上できます。ぜひ自社の従業員教育にも取り入れてみてはいかがでしょうか。