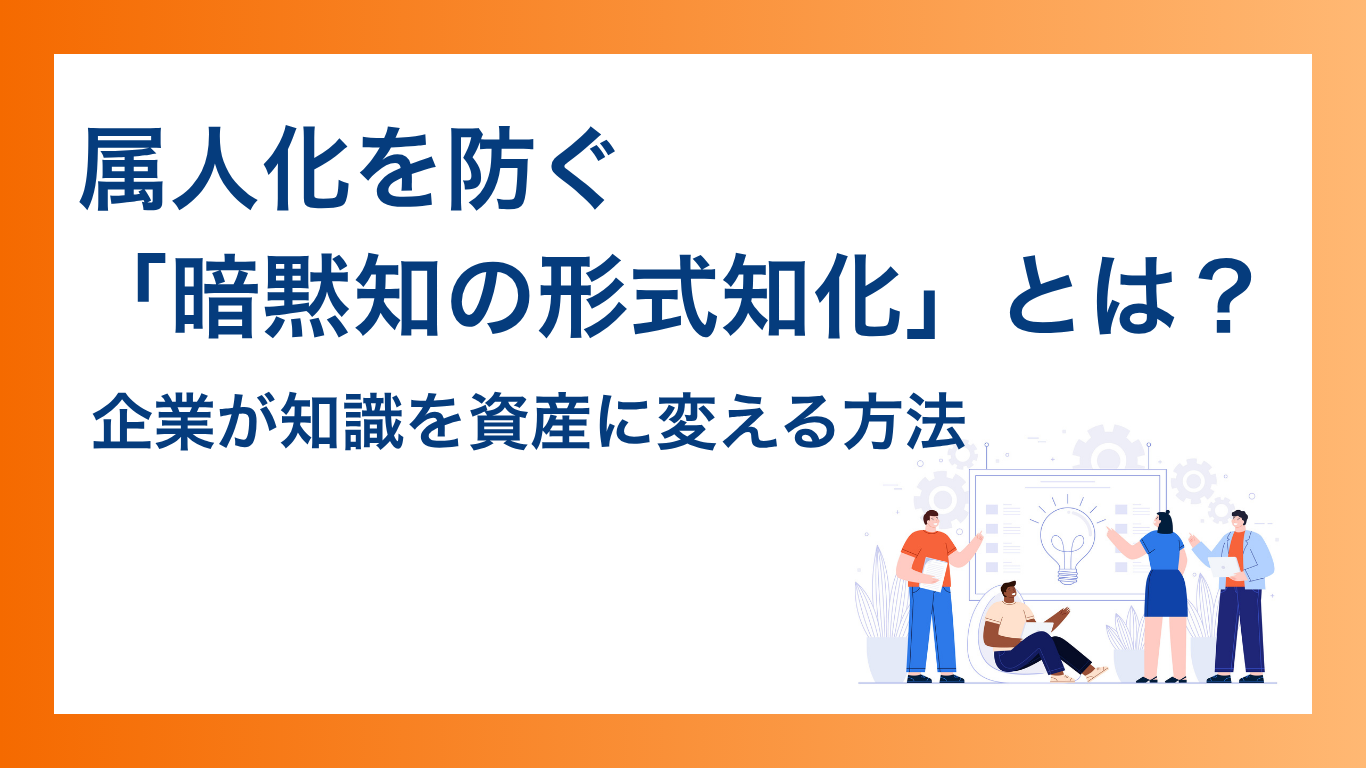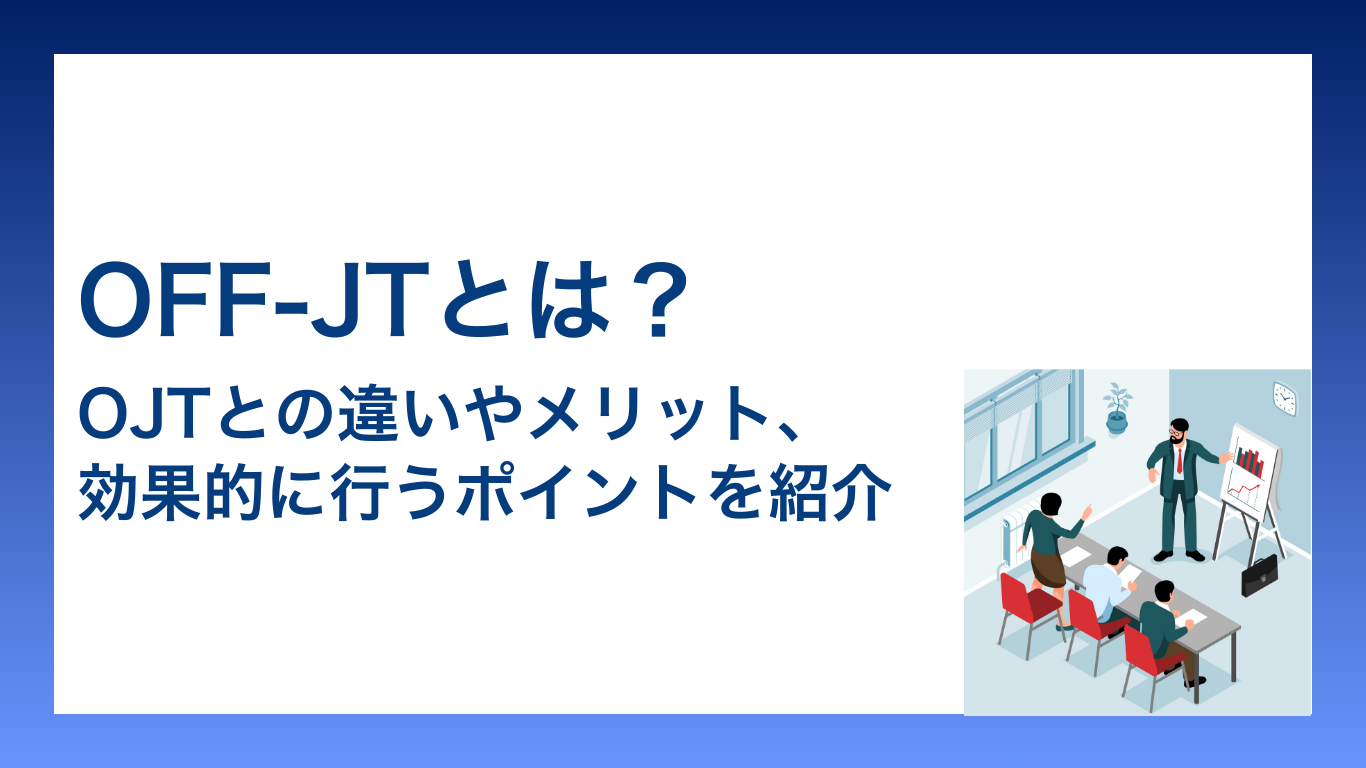eラーニング(e-learning)とは、「electronic learning」の略で、インターネットやデジタル技術を活用した学習方法を指します。パソコン、スマートフォン、タブレットなどを通じて、場所や時間にとらわれず学ぶことができる柔軟な教育手段です。
本記事では、eラーニングの基本から、企業での活用方法、システムの選び方、そして最新トレンドや企業での活用例まで解説します。
eラーニングとは
総務省のウェブサイト「e(イー)ラーニングを活用しよう」から引用すると、以下のように定義されています。
パソコンやスマートフォン、タブレットなどの情報機器を使って、インターネットなどを経由して学習することをeラーニングと呼びます。この「e」とは、electronic(エレクトロニック:電子的な)という意味です。
eラーニングの学習教材などは、パソコンなどにダウンロードして使うものと、クラウドサービス型のものがあります。クラウドサービス型は、パソコンなどの機器にソフトをダウンロードして利用するのではなく、使いたいときにインターネットでサービスにアクセスして利用します。
eラーニングを活用するメリットは、企業・学習者双方にとって多岐にわたります。
以下に主なメリットを5つご紹介します。
1. 時間・場所にとらわれない学習が可能
パソコンやスマートフォンなどのデバイスとインターネット環境があれば、いつでも・どこでも受講できます。移動時間や物理的に拘束される時間もないため、受講者は自身のスケジュールに合わせた柔軟な学習が可能になります。
2. 教育コストの削減
対面の研修の場合、講師の派遣や研修会場の手配、資料の準備といった手間と時間が必要になりますが、eラーニングであれば物理的に必要となる準備物は不要です。そのため、研修運用者の時間的・金銭的コストを削減できます。
また、受講人数が増えてもかかる負荷は少ないため、スケーラビリティに優れています。
3. 進捗管理・効果測定がしやすい
学習の履歴やテスト結果などをシステム上で管理できるため、受講者の状況を可視化しやすくなります。よって、定量的なデータをもとに、教育施策の見直しや改善がしやすくなります。
4. コンテンツの再利用・更新が簡単
一度作成したコンテンツは繰り返し利用できるので、新しい人が入るたびに行うような研修は何度も同じ内容をする必要がなくなり、工数の削減が見込めます。
また、法改正や業務変更に伴う修正も、オンライン上で管理するコンテンツであれば、スピーディに対応・差し替え可能なので、いつまでも古いままの情報を参照していた、ということも起きにくくなります。
5. 学習の個別最適化
ひとりひとりの進捗や理解度に合わせて学習を進めることで、画一的な集合研修よりも各人の理解度や知識レベルに最適化された学習が可能になり、高い学習効果が期待できます。また、自主的に学びたい人が、必要なタイミングで必要な学びを得やすくなります。
eラーニングとLMS(学習管理システム)の関係は?
「eラーニングとLMS(Learning Management System)は密接に関連していますが、役割や意味が異なります。以下にわかりやすく違いをまとめます。
eラーニング
eラーニング(e-learning)は、「インターネットやデジタル技術を活用して行う学習・教育手法」の総称です。動画講義・スライド資料・クイズ・シミュレーション教材など、コンテンツの形式はさまざまで、個人学習から集合研修の補助まで幅広く活用されています。
LMS
LMS(Learning Management System)は、eラーニングを「管理・運用」するためのシステムです。学習コンテンツの配信、学習進捗の記録、成績管理、受講状況の可視化などができる機能を兼ね備えています。たとえるなら、YouTubeの「動画コンテンツ」がeラーニングにあたり、「YouTubeというシステム」がLMS、と言えるでしょう。
企業においては、LMSを導入し、その中でeラーニングコンテンツを提供する形が主流です。LMSなしでeラーニングを提供することも可能ですが、大規模運用や効果測定を行うにはLMSの活用が適しています。
関連記事:【企業向け】LMSとは?主な機能と導入メリット、活用法を紹介
どんな学びができるの?
eラーニングで提供される教育コンテンツには、学習目的や対象者、業種・職種によってさまざまな種類があります。以下に代表的な種類と具体例を挙げます。
ビジネススキル系コンテンツ
- 目的:新入社員〜管理職まで幅広く対応。社会人として必要な知識やスキルの習得。
- 主な内容例:
- ロジカルシンキング、プレゼンテーション、タイムマネジメント
- ビジネスマナー、報連相(ホウ・レン・ソウ)
- コミュニケーション、クレーム対応
- ロジカルシンキング、プレゼンテーション、タイムマネジメント
IT・デジタルスキル系
- 目的:業務で必要なITリテラシーやDX対応力の習得。
- 主な内容例:
- Microsoft Office(Excel、Word、PowerPoint)の操作
- 情報セキュリティ・個人情報保護
- プログラミング(Python、Java、HTML/CSS)
- データ分析、AI基礎、生成AIツールなどの活用法
- Microsoft Office(Excel、Word、PowerPoint)の操作
法務・コンプライアンス系
- 目的:社員全体への法令順守教育。トラブル・リスク防止。
- 主な内容例:
- ハラスメント防止(パワハラ・セクハラ)
- 労働基準法や労働安全衛生法の基礎
- 下請法、独占禁止法
- 情報漏えい対策
- ハラスメント防止(パワハラ・セクハラ)
語学
- 目的:海外取引・外国人対応のための語学力向上。
- 主な内容例:
- ビジネス英語、TOEIC対策
- 英会話(メールや電話応対、会議での表現)
- ビジネス英語、TOEIC対策
業界・職種別専門教育
- 目的:専門知識・技術の習得や認証資格対策。
- 主な内容例:
- 【製造業】安全衛生、5S、品質管理、作業手順
- 【医療・介護】感染症対策、接遇、倫理研修
- 【金融】コンプライアンス、融資・保険の基礎、資産運用知識
- 【営業】提案営業、ヒアリング力、商談の進め方
- 【製造業】安全衛生、5S、品質管理、作業手順
マネジメント・リーダーシップ
- 目的:管理職候補・現職向けの能力開発。
- 主な内容例:
- 部下育成、1on1の進め方
- 評価・フィードバックの仕方
- チームマネジメント、リスク管理
- 部下育成、1on1の進め方
新入社員研修・階層別研修
- 目的:新しい仕事や役職・役割への心構え、早期適応サポート。
- 主な内容例:
- 入社時研修(社内ルール、就業規則、社内ツールの使い方)
- 若手社員の意識改革、配属前の基礎知識教育
- 中堅社員の役割認識、リーダーシップ基礎
- 入社時研修(社内ルール、就業規則、社内ツールの使い方)
自己啓発・キャリア支援
- 目的:社員の自律的学習やキャリア形成を支援。
- 主な内容例:
- キャリアデザイン、アンガーマネジメント
- メンタルヘルス、ストレスマネジメント
- 自己分析、履歴書・職務経歴書の書き方
- キャリアデザイン、アンガーマネジメント
eラーニングシステムの選び方
eラーニングを導入・選定する際には、以下のようなポイントを重視することで、効果的かつ継続的に活用できる環境を整えられます。
目的・対象に合った教材・コンテンツがあるか
自社が行おうとしている研修や教育の目的(例:compliance研修、階層別研修、特定職種のスキル習得など)に合った内容や教材が用意できるかどうかチェックしましょう。社員のレベルや職種、部門に応じたカスタマイズができると、より効果的な学習が可能になります。
また、中には自社で作成したオリジナル教材をアップロード・管理できるものもあるので、必要に応じて検討してみるのもいいかもしれません。
LMS(学習管理システム)の機能性
eラーニング教材を視聴・管理するシステム(LMS)の使いやすさもポイントです。受講・進捗管理のしやすさや、受講後のテスト結果の可視化など、学習の「見える化」ができるか、また未受講者への自動リマインド通知、スコア分析、レポート出力などの管理・分析機能が備わっていると、工数の削減や研修自体の改善がしやすくなります。
操作性・ユーザビリティ
継続的に受講してもらうためには、受講者が直感的に使えるシンプルなUI/UXであるかも重要です。スキマ時間に学習するという観点では、スマートフォンやタブレットなど、マルチデバイスでストレスなく視聴できるインターフェースであることが望ましいです。
また、マニュアルが充実しているか、サポート体制が整っているかも継続利用する上でのチェックポイントになるでしょう。
情報セキュリティ
情報漏洩リスクや利便性のトラブルを回避するため、以下のようなポイントを押さえておくことが理想的です。
- 通信の暗号化(SSL/TLS):ログイン情報・学習データがSSL/TLSで暗号化されて送受信されているか
- 認証・アクセス制御:シングルサインオン(SSO)対応やIP制限ができるか?
- データ保管・管理の体制:学習履歴や個人情報が保存されるサーバーの場所はどこか(国内 or 海外)?ISMSなどの情報セキュリティ認証を取得しているか?
- 利用ログ・操作履歴の取得:ユーザーのログイン履歴、教材の閲覧履歴、ダウンロード履歴などを記録・追跡できるか?
費用対効果
利用にかかる費用としては以下のような項目があります。
- 初期費用
- 月額費用
- サポート費用
- オプション機能費用
利用するアカウント数や契約期間などによって変動するので、事前にかかる費用を見積もっておきましょう。
また、導入にあたって費用対効果の数値を求められるケースもありますが、研修の効果というのは長期的にみていく必要があり、かつ定量的に測るのが難しいかと思います。その場合、導入しなかった場合にかかる研修運用者にかかる工数やリスクを提示することで効果を示すというのも一案です。
拡張性・他システムとの連携
利用する人数の増減に柔軟に対応できるような仕組みやプランになっているか?また、社内ポータル、タレントマネジメントシステム、勤怠管理など、現在使用している外部システムとの連携が可能かどうかもチェックしておきましょう。また、よくある失敗を回避するために以下のポイントには注意しましょう。
- 目的があいまいなままシステム導入を進める
- 使いこなせないほど多機能なツールを選定する
- 利用者のITリテラシーや環境に合わないシステムを導入する
おすすめのeラーニングシステム5選
以下は、企業向けに多く導入されているeラーニングシステムの一部です。
Cornerstone on Demand

URL:https://www.cornerstoneondemand.com/jp/
世界的に利用されている統合型eラーニングシステムで、従業員数の多い企業やグローバル企業に適しています。eラーニング用のシステムだけでなく、採用・評価・キャリアなど一貫した管理が可能で、スキルギャップの可視化やAIを活用した従業員ごとのパーソナライズされた学習カリキュラム提案などを得意とします。
また、利用できる学習教材は22,000以上あり、コンプライアンスや各種言語、マネジメントやプログラミングなど、業種・業界・ポジション横断で幅広くカバーしています。
CAREERESHIP

URL:https://www.lightworks.co.jp/services/careership
チーム/部門/法人ごとの教材配信や管理者権限を自由に設定でき、またログイン後のTOPページをグループ別にカスタマイズできるので、受講グループごとカスタマイズしたページ設定ができます。導入から運用まで、手厚いサポートの準備があるのも特徴です。
利用できる学習教材は300タイトル/1,000本以上、新入社員や管理者などポジション・役職別や、コンプライアンスや戦略的思考など、企業に務める従業員向けのコンテンツが充実しています。さらに、オリジナル教材の受託制作や既存教材のカスタマイズにも対応しています。
learningBOX

URL:https://learningbox.online/
低コストかつシンプルなUIで、はじめてでも導入ハードルが低いのがこのサービスです。動画・PDF・レポート・暗記カード・クイズ問題・タイピング教材など、対応フォーマットが複数あり、またAIがクイズ・暗記カードを自動生成し、レポート分析やフィードバックコメントを支援してくれるのも特徴です。
AIによる顔認証やブラウザ監視など、不正対策機能が充実しているため、受講必須の研修を確実に実施する必要がある企業での利用に適しています。利用できる学習教材は52テーマ/480本以上、ビジネスマナーやコンプライアンス、情報セキュリティなどです。
Shcoo for Business

Schoo for Businessは、株式会社Schooが提供する法人向けオンライン学習サービスで、個人向けSchooの動画教材(録画+ライブ配信)を法人向けに拡張し、組織学習に適したプラットフォームとして提供しています。
本サービスの特徴はなんといってもそのコンテンツ数。利用できる学習教材は9,000本以上、かつ毎月50本以上のコンテンツが更新され、新しいスキルやトレンドを継続的に学習できます。多数の社員に対して幅広いスキルを一律で提供したい企業や、自律学習・リスキリングを組織的に推進したい企業に有効です。
eラーニングは今後どう発展していく?
日本でも一般化したeラーニングの活用ですが、ここでは海外でのトレンドをいくつかご紹介しつつ、今後日本でもどのような発展があるのか予測してみたいと思います。
AIパーソナライズドな学習設計(アダプティブ・ラーニング)
AIによるパーソナライズとは、学習者ひとりひとりに最適な学習カリキュラムをリアルタイムで提供する仕組みのことです。世界中で使われている語学学習アプリ・Duolingoは、このAIを使った学習のパーソナライズ化していることで有名です。ですので、実はもう体験したことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
このトレンドには、これまでのバックグラウンドや知識レベルがバラバラの従業員に、従来型の企業側から提供する一律の研修内容では効果が薄い、かと言って、個別最適化されたカリキュラムを設計するにはリソースが足りない、という課題感が背景にあります。
たとえばアメリカの世界的テクノロジー企業・IBMは、独自の学習AIプラットフォームを構築して、各従業員ごとに、職務/過去の受講履歴/パフォーマンス/キャリアパスなどのデータを分析させ、そのデータをもとに個別の学習カリキュラムを自動生成しています。
さらに、スキルギャップ分析もAIが行い、従業員の現状と次に学ぶべきことも提案してくれます。その結果、IBMは研修の運用にかかる時間を大幅に短縮し、従業員満足度とコース修了率を向上させることに成功しました。
出典:Case Studies: Successful AI Adoption In Corporate Training
VRを活用した没入型教育
これまでの座学主体の学習から、VR(バーチャル・リアリティ)技術を使うことで、より実務に近い形で社員教育が実現できるようになりつつあります。
アメリカのWalmart社では、VRとeラーニングシステムを活用して、接客/クレーム対応/リーダーシップなどの実践的シミュレーション学習を導入。 これにより、従来の研修時間を8時間から15分に短縮、学習者の 70% がトレーニング後のスキル評価で高いスコアを獲得し、学習定着率が向上したそうです。
出典:Walmart cuts training time by 96% with immersive learning
ゲーミフィケーション要素の進化
ゲーミフィケーションとは、その名の通りeラーニングにゲーム的要素を取り入れることです。ログインや課題をクリアするごとにポイントやバッジがもらえたり、ランキング制を組み込んだ設計になっていたりと、多種多様な仕掛けがあります。
どうしても企業主導の研修というものは、受講者は受動的な受講態度になりがちですが、研修に参加する従業員のモチベーションアップと、継続率向上のためにゲーミフィケーション要素を取り入れることは有効かもしれません。
多国籍テクノロジー企業のヒューレット・パッカード(HP)は、販売力強化のための製品知識を身につけてもらうため、販売代理店への販売トレーニングにゲーミフィケーション要素を取り入れました。研修教材は物語風のものを採用し、受講者は研修を進めるとポイントを獲得、そのポイントは実際の景品と交換可能なものでした。
結果、受講者の31%が週1回以上学習に参加し、研修の完了率が50倍まで増加したそうです。
出典:HP boosts channel sales revenue through higher engagement with training
上記のケースから、これからeラーニングの進化の方向性として、AIパーソナライズ・VRを活用した没入型教育・ゲーミフィケーションといったトレンドが、日本にも到来するのではないでしょうか。
まとめ
eラーニングは、単なる「オンライン学習」ではなく、企業や教育機関にとって戦略的に活用できる学習の仕組みです。コスト削減・学習の効率化・教育の標準化といった利点があるだけでなく、AIやVRなどの最新技術と組み合わせることで、さらに進化を遂げています。導入する際は、自社の教育目的に合ったシステム選びがカギとなります。
この記事を参考に、ぜひ自社のeラーニング活用を一層効果的に進められることを願っています。